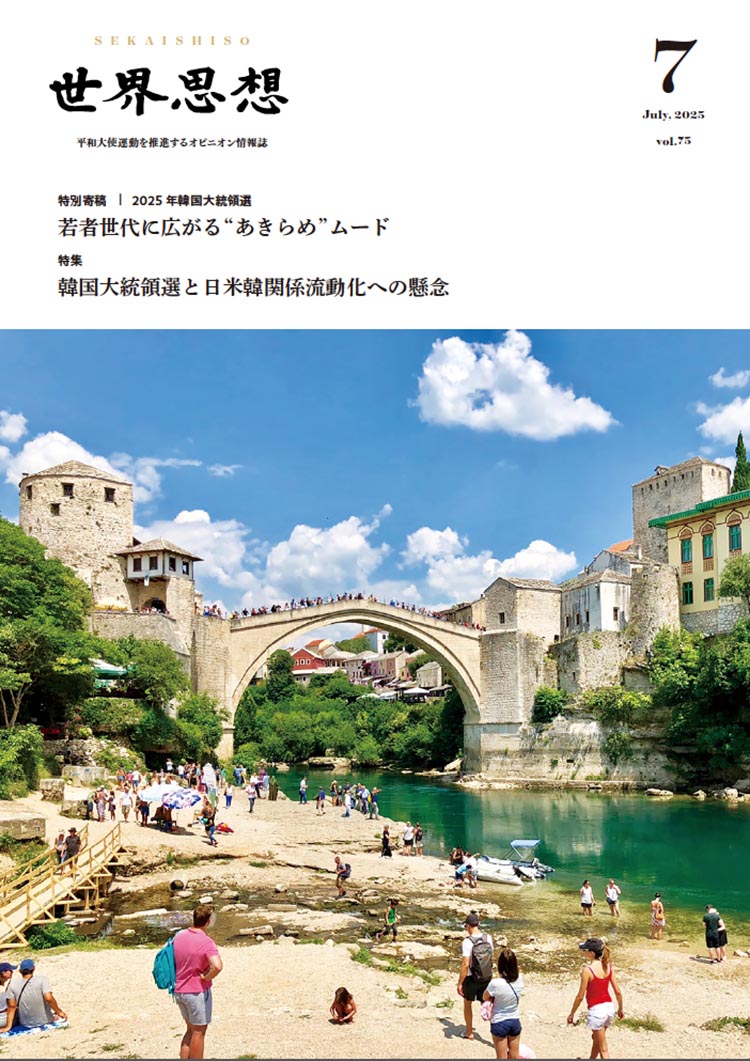「世界思想」7月号を刊行しました。
今号の特集は「韓国大統領選と日米韓関係流動化への懸念」です。
ここではPart2 米国の視点から見た韓国大統領選挙を紹介します。
いかなる国・地域においても自衛のための戦術は変更される。ましてや一民族が分断状況にある地域や国においてはなおさらのこと。さらにその分断が、内発的である以上に外部要因が主な理由であればなおさらのことだろう。朝鮮半島はまさにそのすべてを内包している。
北朝鮮の極端とも見える動きは、多分に「トランプ大統領再登場」が大きな要因となっているといえるだろう。金正恩朝鮮労働党総書記は2020年の大統領選においてもトランプ氏の当選を期待していたとの指摘がある。
現状の打破は、自国だけでは極めて難しい。とりわけ国境が地続きの中国やロシアとのかかわりがあり、困難である。周辺諸国を抑え、あるいは協力を得なければならない。もちろん「自主」が軸となっての関係構築である。 韓国の大統領選挙期間に合わせ5月25日に、同選挙システムを監視するため米国の「国際選挙監視団」が訪韓した。モース・タン(元国際刑事司法大使)、ジョン・ミルス(元米国防総省サイバーセキュリティー政策局長)、グラント・ニューサム(元米海兵隊戦略将校)、ブラッドリー・テイアー(米シカゴ大政治学博士)各氏ら、多方面の分野の専門家で構成。26日~6月4日の10日間に渡り、韓国の選挙を直接観察し、選挙の手続き面での公正性を検証し、国際社会に向け報告書を公表するのが任務だった
国際選挙監視団の「声明」について
「韓国の投票システムは手続きの透明性が保障されていない。有権者は常に疑問を投げかけてきたが、政府と中央選挙管理委員会は閉鎖的な態度を変えないため制度に対する信頼性は低い。今後は変化が必要だ」
5月29日、監視団はこのような「緊急声明」を発表し、「韓国の選挙制度は10点満点の3~4点レベル」の評価とともに、5月29~30日の期日前投票制度について、電子開票システムがサイバー攻撃を受ける可能性、また選管が正当な監視活動を行う者を警察に逮捕させるなど、選管の中立性・公平性に関わる問題点を指摘した。
さらに、前節でも触れたように、6月3日の即日投票と、期日前投票との極端な得票分布の乖離 があったにもかかわらず、マスメディアにより発表された「出口調査」結果が、即日投票分(李在明氏37・96%、金文洙氏53・00%)よりも、むしろ本来は開票前に分かるはずのない期日前投票の結果(李氏63・72%、金氏26・44%)に近いのは明らかに不自然だった。
米国の「当惑」を象徴するレビット報道官
こうした選挙監視団の報告をトランプ米政権も把握していたはずだが、李在明氏が大統領選で当選した事実に、ある種「当惑」していたことを示すエピソードがある。それは、トランプ政権の「顔」として歯切れのよい明快な答弁から、保守派層の間ですこぶる評判の良かった米国ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官が会見で示した珍しいハプニングだ。
月3日(現地時間)、ホワイトハウスで行われた記者会見の途中で、記者団から「韓国の大統領選挙結果に対する何らかの見解はあるか」という質問を受けると、レビット報道官は「もちろんある」と答えた。 そして壇上に立ったまま、事前に準備してきた書類から回答関連の文面を探した。レビット氏は「確かにここのどこかにあったはずなのに…」と関連書類を探したものの、結局準備してきたものを「確認」できず、苦笑しながら「(韓国大統領選への見解を今は)持っていないが、間もなく見解を発表する」と話すにとどめた。
この「ハプニング」直後に国務省でも記者会見が行われたが、同省のタミー・ブルース報道官は米政府の反応を尋ねる質問に対して「(韓国で大統領)選挙があり、当選認証(certification) を待っている」とし「その結果が出れば声明を発表するだろう」と答えた。