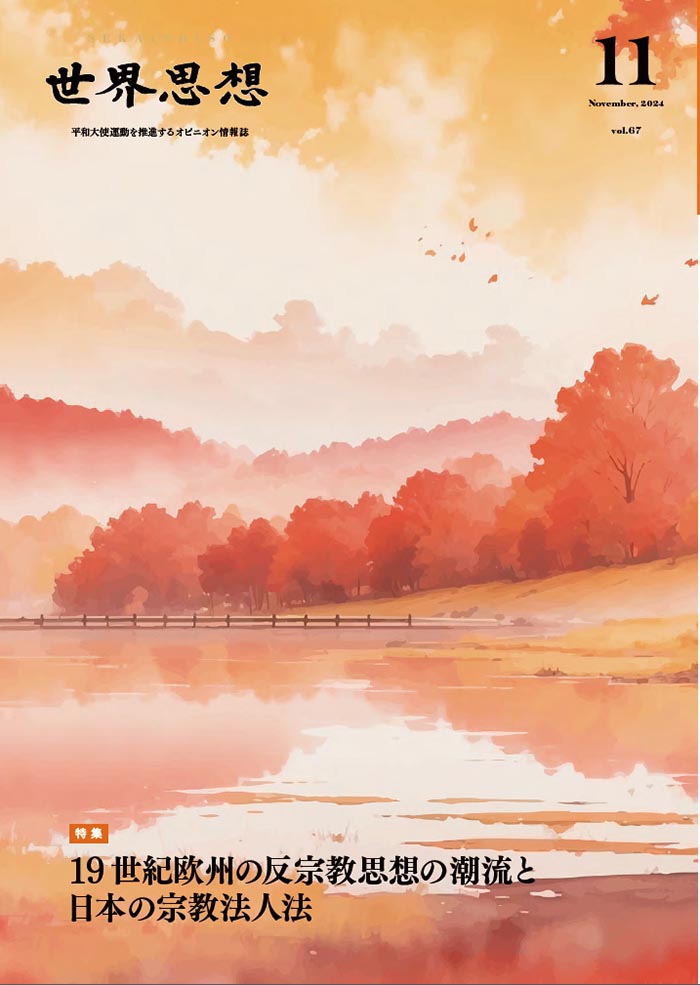「世界思想」11月号を刊行しました。
今号の特集では、さる9 月27 日に韓国で行われた平和宗教学会学術大会における
大塚克己UPF-Japan 議長の講演内容(要旨)を紹介します。
フランス革命とその後の反宗教理念
フランス・パリ・オリンピックが8月12日、閉幕した。そこで大きな話題となったのは開会式の記念公演だった。ローマ教皇庁(バチカン)が、異例の批判声明を出した反キリスト教的開会式行事は、〝多様性〟〝表現の自由〟などの言葉では表現できない、とても酷ひどいものだった。
この開会式行事で最も醜悪であったものが、1789年のフランス革命において断頭台で処刑された王妃マリー・アントワネットの血塗られた首の場面ではなかっただろうか。フランスに長年住んでいた筆者にとって、この行事はフランス社会の倫理的混乱を示すものだ。
しかし、当のフランス人は私たちが思う以上に革命を誇りに思っている。そのスローガンである「自由、平等、友愛」は、フランス国家の基本理念となっている。
ご存知のように、フランス革命は既存の権力、すなわち王政やカトリック教会への反発が動機となった。王政のもとでの「政治的不自由と不平等」、カトリックの教えによる「精神の自由の束縛」、経済的には拡大する「貧富の差」などへの不満が爆発した革命であった。こうした不平等や不満をキリスト教会は克服することができなかった。
革命後の反宗教の思想潮流
その後のフランスの歴史を見れば、革命が成功であったとはいえない。しかし、フランス革命の「自由、平等、友愛」の理想が世界に与えた影響は大きなものがあった。
こうした理想を宗教なしで実現しようとした歴史もあった。代表的なものが共産主義革命だ。共産主義者は、共産主義こそ自由と平等の理想を実現できる最も科学的方法であると考えたのだ。もちろん、彼らから見れば「宗教」は人々の自由を束縛するものとして攻撃の対象だった。
それらの思想が19世紀の反キリスト教的理念が、ヨーロッパから世界に拡大した。その理念を現実の社会に適応したのが20世紀であったと言えよう。
19世紀の反キリスト教の思想潮流
18世紀から19世紀にかけての「神からの離反」の思想的潮流は、大変大きなものだった。代表的人物がダーウィン、フロイト、マルクスそしてニーチェなどだ。これらの人物が日本の学者や社会に与えた影響は、あまりにも大きなものがあった。
ダーウィンの「環境適応」
チャールズ・ダーウィン(1809〜82年)は今日もなお、世界的に大きな影響を与えている進化論を提唱し、結果的に神の創造論に挑戦することになった。しかし、彼の「科学的」と言われるその研究は、いまだ「そのような考え方」というレベルにあることを理解しなければならない。同時に、彼の「環境適応」「適者生存」の考え方が優生保護思想という、人権蹂躙と殺戮という大きな悲劇を生んだことも忘れてはならない。
ダーウィンの「適者生存」思想を最もよく表現している言葉がある。欧米人なら良く知っている言葉だ。
〝生き残る種というものは最も強いものでも、最も知性があるものでもない、変化に対応できたものである〟
では、科学的にも実証されていない「適者生存」という考え方をそのまま社会に適応したらどうなるだろうか。
国家政策としての優生政策
今年7月3日に日本の最高裁判所で、1948年に成立した旧優生保護法は違憲であるとの判決が出され、大きな話題となった。ヨーロッパ、アメリカの優生思想をもとに、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とし、日本は国家政策として、精神障害、知的障害、神経疾患、身体障害などを抱える人に対し、強制不妊手術を行った。人権無視のこうした法律が、長年にわたって日本に存在したことは大きな驚きだ。
優生思想はダーウィンの祖国であるイギリスから始まり、やがてアメリカで広がった。アメリカ国内では、優生政策による国家的避妊手術のロードマップが1914年に発表されている。
そして、その年の末までにアメリカ12州で強制避妊法が成立。この優生政策は1924年に移民法として確立した。そして、「劣った人々」とされたイタリア人、中南米人、アフリカ人、アジア人などの移民が制限されることになった。
このアメリカの優生保護法を、国家政策として徹底的に実行したのがドイツのヒトラーである。1934年以来、3年間で20万人を不妊化したといわれるナチスは、北欧系白人の純血を守るためと称して、35年に「ニュルンベルグ法」と呼ばれる法律を制定した。そして、「不適者」を安楽死させていった。
このヒトラーの優生政策は、アメリカの優生学者たちに好意的に受け止められた。そして、ドイツやヨーロッパ地域のこうした優生保護法を無批判に導入したのが、日本の優生保護法であった。
「信教の自由」についての議論も同様であり、日本では理念としての理解が浅く、第2次世界大戦後に、アメリカを中心とする占領軍が与えたものをそのまま受け取っただけのものが多く見受けられる。
徹底的な無神論主張したフロイトとマルクスジークムント・フロイト(1856〜1939)は「性衝動は罪だ」という伝統的カトリックの原罪論から人々を解放したと言える。性衝動こそが我々の発展と成長の原因であるとも主張したのだ。フロイトは、科学が発展すれば宗教は不必要になるとも主張した。彼は、人が信仰を持った状態は「強迫的神経症状態」であり、「宗教は幻想」であると考えた。そして、キリスト教会の「牧会」の概念を、心理学的カウンセリングや医療的処置に置き換えてしまった。
カール・マルクス(1818〜1883)は徹底的な無神論を主張し、「歴史を動かしてきたのは神の摂理ではなく階級闘争だ」と闘争を煽動した。共産主義革命の悲惨さについては説明する必要がなかろう。人間の類的本質を「労働」と考える共産主義者にとって、「労働しないものは人間ではない」ということになる。
ニーチェによる「神殺し」宣言 これらの19世紀の思想は科学的で、啓蒙的、実証的で、合理的であると主張された。神を離れた科学万能主義、唯物主義が世界に拡大した。
19世紀の末、哲学者のフリードリッヒ・ニーチェ(1844〜1900)は『悦ばしき知識』(Diefröhliche Wissenschaft、1882)の中で、明確に反宗教、反キリスト教を宣言した。
神は死んだ。死んだままである。そして、我々は神を殺したのだ。
このニーチェの「神は死んだ、神を殺した」という言葉で20世紀が始まった。神を殺した理念で自由と平等が実現した理想国家を実現できたのだろうか。西洋化を進めた日本には、これらの思想がまさに洪水のように流れ込む結果となった。当時の日本の思想界、宗教界にはこれらに対抗する力はなかったのだ。