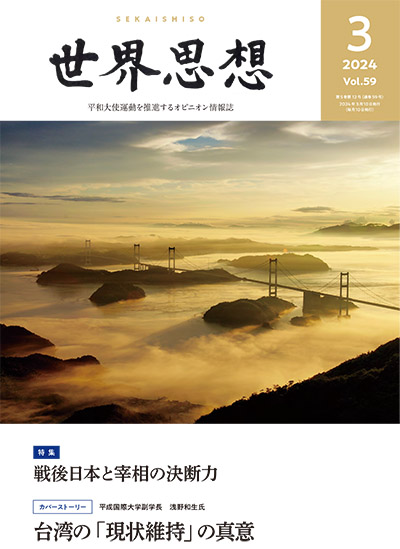「世界思想」3月号を刊行しました。
今号の特集は「戦後日本と宰相の決断力」です。
ここでは特集記事の一部をご紹介します。
2020年代に入り、世界はまさに乱世に突入している。東西冷戦と米国一極の時代、日本外交は基本的に「対米追随」に終始し、それで事足りていた。しかし、米国の力が相対的に弱まった今、もはや無責任な米国頼みでは済まされない。複雑なパワーゲームが展開される荒海の中で、自国を守り、望ましい国際秩序の形成に向かうことができるか。わが国の舵取りを担う総理の責任は重大だ。
ただし、わが国のような民主主義国家においては、政権を選択するのは主権者たる国民自身である。大統領を直接選ぶ米国などとは異なるが、政権与党を選ぶのは国民だ。また、与党内の権力闘争も国民世論の動向と無縁ではない。果たして、我々は乱世にふさわしい指導者を見極める目をもっているだろうか。
乱世に求められる指導者の資質は、平時とは異なる。世界を見渡せば、ウクライナに侵略戦争を仕掛けたロシアのプーチン大統領、アジア・太平洋の覇権確立を目論む中国の習近平国家主席、闘争的な性格をむき出しにしつつある北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記、米中2極に割って入ろうとするグローバルサウスの雄、インドのモディ首相など野心的で強力な指導者たちがひしめいている。そこに対峙する見識も覚悟も胆力もない者がトップに立った場合、わが国の命運は尽きてしまうだろう。
乱世の指導者として最も問われるべきは、適確な情勢認識と、守るべき価値を明確にする国家観、そして「自ら省みて縮くんば、千万人といえども吾往かん」という決断力だ。

左から中曽根康弘首相、岸信介首相、吉田茂首相 ※内閣官房内閣広報室 CC BY 4.0 DEED
チェンバレンとチャーチル
歴史の教訓として、指導者の情勢認識や決断力が1国家のみならず、世界の命運を決した事例を確認しておこう。舞台は第2次世界大戦時の英国、東西冷戦末期の米国だ。
まず第2次大戦前、ナチス・ドイツの台頭を招いたのはチェンバレン英首相をはじめ、主要国首脳による融和政策だった。重要な転機となったのは、チェコスロヴァキアの領土(ズデーテン地方)のドイツへの併合を認めたミュンヘン協定(1938年)である。
当時、既にヒトラーのドイツは国際連盟を脱退(1933年)し、再軍備を宣言(35年)。さらに国際条約を無視してラインラントに進駐(36年)、38年3月にはオーストリア併合へと突き進んでいた。
「生存圏」の拡張に突き進むドイツは、自民族の居住者が多いことを理由にチェコスロヴァキアにズデーテン割譲を要求、戦争も辞さないという強硬姿勢を示していた。
事態が緊迫した1938年9月、チェンバレン、ヒトラーを含む英仏独伊4カ国の首脳が集まり、ミュンヘン会議が開催された。結論として、ドイツが今後、重要な対外行動をとる際には英国と協議するという枠組みを作る一方で、ズデーテンのドイツ併合が容認されてしまった。
当時、英国などの保守勢力が最も警戒していたのは共産主義国家ソ連であり、そこから拡散する革命の脅威であった。つまりチェンバレンの対独融和には、ヒトラーを懐柔することで、対ソ抑止力として利用しようとする思惑があったのである。しかし、このミュンヘン協定はヒトラーの生存圏拡大の動きに対して「英仏の実力行使はない」という誤ったメッセージを与えるとともに、軍事力強化の時間的余裕を与えてしまった。その後、ナチス・ドイツが引き起こした国内外の悲劇は言うまでもない。英国も首都ロンドンを空襲されるなど、国家存立の危機に追い込まれた。
ミュンヘン会議は当初成功と見なされ、チェンバレンは国王、国民の大歓迎を受けたが、かねてよりドイツの軍備増強を警戒していたチャーチルは宥和政策に反対し、自派議員30人とともに批准決議を欠席した。
「反ファシズム」で一貫し、ドイツのポーランド侵攻(1939年)による第2次大戦勃発後も、チャーチルは早期講和ではなく、ドイツとの生存をかけた戦いを主張した。40年5月の就任以降は戦時の首相として強い指導力を発揮。英国民を奮起させ、戦争の勝敗を決定づける米国の参戦を粘り強く働きかけた。
良くも悪くも信念の塊であったチャーチルの施策には毀誉褒貶も激しく、敵も多かった。ドイツ降伏直後に行われた総選挙で彼は退陣することとなるが、英国を存亡の危機から救った功績が色あせることはない。まさに彼は有事の指導者、乱世の大宰相であった。